サイエンスカフェみたか「植物の生き方と情報伝達」
2025年5月22日、サイエンスカフェみたか「植物の生き方と情報伝達」をオンラインで開きました。講師は東京理科大学 教授 朽津和幸さんでした。5月のサイエンスカフェは「国際植物の日」のイベントとして登録して、行いました。
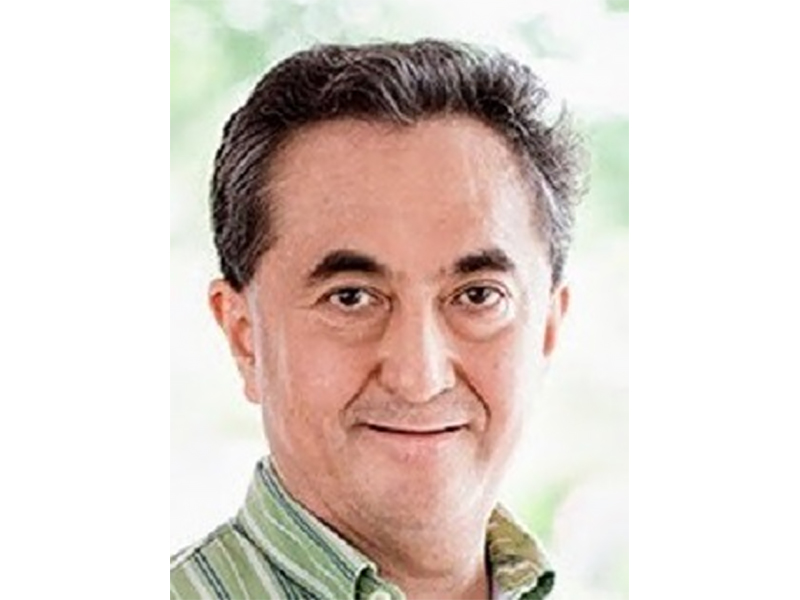
朽津和幸さん
お話の概要
私は東京理科大学野田キャンパスで研究、教育、いろいろな人とのコミュニケーションをしている。東京芸術大学デザイン専攻の皆さんから「植物をよく観察するが、植物体内でなにをしているかわからない」ということで講義を依頼されたこともあり、理系でない人とも植物のお話をすることがある。
今回のサイエンスカフェは国際植物の日のイベントだが、今日、5月22日は「生物多様性の日~すべてのいのちと共にある未来へ」でもある。
人類が化石燃料を使いつくそうとしている結果、人間活動は地球の限界を超えたといわれており、気候変動危機、窒素循環の危機、生物多様性の危機を招いている。光合成生物である植物こそエネルギー危機への貢献が期待される。
植物とは
植物的生き方とは、太陽をエネルギー源として無機物から生物の体を構成する有機物を合成できる。シアノバクテリアがこの生き方を始め、すべての植物はこの生き方を採用した。これに対して動物的生き方とは、動き回って植物や植物を食べた生物を食べる。このほかに寄生者としての生き方もある。
地球上に最も繁栄しているのは植物。植物は光合成を行って生きている。光合成とは、光エネルギーを使って二酸化炭素から有機物を作る営みで、水から電子を得るため、酸素が排出される。そのことが、呼吸する動物などの生物の繁栄につながった。シアノバクテリアが始めたこの生き方ができる生物の家系図をみると、さまざまな系統の生物が植物的生き方をしている。生物は動物的、植物的、微生物的な生き方を選べる。ミドリムシは光合成ができ、植物的な生き方をしている。
ワカメとノリは生物の系統樹では大きく離れている。アオサなどの緑藻は陸に上がった植物の先祖といえる。5億年前に太陽をもとめて植物は上陸した。5億年以前の生物はみんな海中にいた。
植物が上陸すると、植物を食べる動物、寄生する微生物も植物の後を追って上陸した。上陸後、植物はクチクラで体を覆い、水分蒸発を防ぎ、気孔ができた。気孔から水が蒸発することで、根から栄養や水を吸い上げ、閉じて蒸発を防ぐ。
植物の五感とセンサー
植物は動かず、環境に反応できないだろうか。
たとえば、外から見てもダイズ豆は生きているかわからない。水がなくて寒い時には発芽しても生きていかれないので発芽しないが、水分、温度が良い状態になると、重力方向に根を出し、重力と反対に茎を出す。モヤシは、葉を光があるときにつくる(暗い時にエネルギーを使って葉をつくるのは自殺行為)。
人の目にはロドプシンという光センサーがあるが、植物には4種類の光センサーがある。情報としての光とエネルギー源の光を使い分けている。
植物に嗅覚はあるのか。植物はエチレンガスをホルモンとして用い、感知できる。青いバナナをもってきてエチレンをあてると黄色く熟す。自分で匂いを発して昆虫とコミュニケーションしている。
味覚はあるのか。ヒトは自分にとって栄養か、毒かを見分けるために味覚を持っている。味覚を自分にとっての敵か味方かを見分ける力とみなすなら、植物は自分の敵か味方かを見分ける仕組みをもっている。植物は病原菌を見分け、撃退する植物免疫のメカニズムを持つ。一方で、味方となる根粒菌とは仲良くする。また菌根菌に栄養をもってきてもらい共生している。
免疫か共生か
微生物は植物と戦うか、give and
takeで共生するかを使い分ける。植物は、ヒトの抗体のようなものとは異なるが、免疫のメカニズムを持ち、病原菌を撃退する。この時、受容体で敵か味方かを見分け、情報処理を行い、活性酸素をつくり出す。
植物は、敵が来ると電気シグナルを発生して情報を伝える。これは、動物の神経で生じる活動電位と似ている。動物の神経は瞬間的に脳に情報を伝えるが、植物は数十秒かかって電気シグナルを出す。
動物の神経細胞の活動電位にはナトリウムイオンが関わっている。植物はナトリウムを使わない進化をしたので、植物にとってナトリウムはむしろ毒。海辺には植物が少ないのは塩があるから。植物の電気シグナルではカルシウムイオン、塩素のマイナスイオンそして水素のプラスイオン(プロトン)が重要。
今では植物の免疫力を高める研究が盛んになってきている。これまでは農薬といえば殺菌剤か殺虫剤が中心だった。日本では安全性の厳しいチェックを受けて農薬を製造している。一方、益虫を殺したり、薬剤耐性害虫・菌ができたりするデメリットがある。そこで植物の免疫を活性化すると病原体を殺し、共生微生物を生かせるような農薬の研究をしている。植物用サプリを目指している。また、微生物が専門の先生との共同研究で、植物の体内に生息し、植物の免疫力を高める効果を持つ微生物について調べている。
植物の情報伝達と情報処理
すべての生物は遺伝的プログラムをもっているのに加えて、周囲の環境をセンサーでとらえて情報処理して適応している(生き方の意思決定をしている)。
動物は脳を発達させ、神経細胞を使って体中から情報を直ちに脳に集め、情報処理をする。植物に脳はないが、長生きし、体を大きくすることができる。体全体で情報を伝え合い、バランスをとることができる。情報を分散処理しているのではないかと思う。植物は、小さなコンピューターを巧みにつないでネットワークを作り、スーパーコンピューターに値する能力を発揮できるような仕組みを形成しているのではないか。
導管と篩管を含む維管束を持つ植物は、そこが情報伝達の媒体となる。導管は死んだ細胞の管で、土から吸収した栄養と水を運ぶ。篩管は光合成により作り出した砂糖などの栄養を葉から貯蔵組織に送る活性の高い細胞の管。ハエトリソウが、虫が触れると葉が閉じたり、オジギソウが葉に触れると閉じたりする非常に早い動きの際にも、維管束を電気信号が伝わる。
しかし、維管束つまり導管や篩管を持たないコケ植物であるゼニゴケも、電気信号を遠くまで伝えられることを発見した。傷をつけるとイオンの動きが引き起こされ、電気信号が出て秒速1-2ミリメートルで波が拡がるように進む。植物が情報を伝えるこうした仕組みの研究を進めている。
動物細胞と植物細胞の違い
動物細胞にはないが植物細胞にあるものとして、葉緑体、細胞壁、液胞がある。葉緑体は、シアノバクテリアを細胞内で飼いならした結果、細胞の一部となった。この他にも植物には分化全能性(すべての細胞が葉、根、茎などになれる能力を持っている)や可塑性という特徴がある。
液胞の役割
動物は細胞分裂して多くの細胞を持つことで体が大きくなる。植物は細胞の体積を制御できるので、液胞の中に水を吸って細胞全体を大きくして、コストをかけずに大きくなる。核や細胞質の体積は変えず、そこが担う細胞の働きは維持したまま体を大きくできる。
液胞はオートファジー(細胞内自食作用)の場でもあり、栄養分をリサイクルし、細胞の再生を制御している。例えばイネが花粉をつくるときにオートファジーが起き、オートファジーは、正常な花粉の形成や、米の品質の制御に重要な役割を果たすことを見出した。
植物は栄養分のリサイクルの仕組みを発達させている。紅葉は緑色の色素、クロロフィルをリサイクルする作用で、緑色の葉が黄色になり、赤くなる。
液胞は、細胞の自殺にも重要な役割を果たしている。植物は、液胞を自爆させて感染した病原菌も殺してしまう。
細胞壁に支えられている人間
細胞壁は水膨れしても細胞が破裂しないようにしている。植物細胞は、細胞壁を固くしたり柔らかくしたりする能力を持ち、細胞壁の固さをダイナミックに制御しながら細胞を大きくする。私たちの衣食住はまさしく植物の細胞壁に支えられている。

研究室風景
先端成長と活性酸素
根には細かい毛があって根の表面積を大きくして水を吸い上げている。根毛の細胞は水膨れしながら、先端を継ぎ足して伸びていく。
めしべの付け根に植物の卵がある。花粉が受粉すると、花粉管の細胞は分裂せずに、卵を目がけて一方向に伸びていける。活性酸素を花粉管の先端でつくりつづけて伸びていく。これは根毛が伸びるときも同じ。活性酸素とは酸素分子と水との中間に位置する、スーパーオキシド、過酸化水素、OHラジカルなどの物質。人間には毒なので活性酸素は悪いものだと思っている人もいると思うが、動物も植物も活性酸素を適正量、積極的に生成して役立てている。
プラズマ工学研究者との共同研究で、プラズマを発生させて植物に当てた。当てすぎると死ぬが、ある程度だと植物の成長が促進されることがわかった。
まとめ
植物は個体を移動できない生物というよりも、大地に根を下ろし、個体を移動させない生き方を選んだ生物と言える。葉を太陽光パネルのように広げ、太陽光をエネルギー源として活用して無機物から有機物、すなわち栄養分を自ら作り出している。そのため、様々なセンサーで周囲の環境を感知して対応している。
植物が私たちに安らぎを与えるのは、私たち動物が植物をパートナーとして進化してきたからだと思う。今は、人が増えすぎて、環境、エネルギー、食料の問題の解決が急務となってきたが、植物の機能をより生かすことで問題解決に貢献できるのではないかと思う。
植物は有機物を自分で作れることから、多種多様な物質を作ることができる、いわば有機化学が得意な生物と言える。植物の免疫システムでつくられる物質は生薬やスパイスなどとして人間が活用している。根での微生物との共生のしくみを構築し、栄養のリサイクルも得意。
植物とどうつきあっていきましょうか。皆さんと考えていきたいと思います。
